「日本型ワーカーズ・コープの社会史~働くことの意味と組織の視点」
 協同総研顧問の石見尚さんが新著を発行されました。戦後のの協同組合運動・生産合作者運動からGHQの政策、企業組合や農事組合法人の法制化、日本型経営と労働者参加、労働者自主生産、そしてワーカーズ・コープなど市民事業型の協同労働と、協同労働を「社会史」に位置づけて豊富な(成功/失敗)事例と共に紹介しています。
協同総研顧問の石見尚さんが新著を発行されました。戦後のの協同組合運動・生産合作者運動からGHQの政策、企業組合や農事組合法人の法制化、日本型経営と労働者参加、労働者自主生産、そしてワーカーズ・コープなど市民事業型の協同労働と、協同労働を「社会史」に位置づけて豊富な(成功/失敗)事例と共に紹介しています。
協同総研でも販売いたしますので、ぜひお買い求め下さい。
「日本型ワーカーズ・コープの社会史~働くことの意味と組織の視点」
石見尚著
単行本: 260ページ
出版社: 緑風出版 (2007/03)
定価:2,400円+税
目次↓↓
まえがき
序章 本書の視点
第1章 日本協同組合同盟の理想と現実
- 協同組合主義者の決起
- 生活協同組合法の制定経過と生産協同組合
- 協同組合同盟リーダーたちの生産協同組合にたいする評価
第2章 生産合作社運動
- 日本生産合作者協会の設立
- 戦後日本の生産合作社
- 中国の生産合作社運動
第3章 GHQの対日労働政策と日本の生産管理闘争の結果
- GHQ労働課長の苦悩
- 生産協同組合にたいするGHQの姿勢
- アメリカの労働者の運動と組織
- 戦後の生産管理闘争が残したもの――企業別労働組合
- 職種別労働組合の職場委員
第4章 企業組合と農事組合法人
- 企業組合の法制化
- 企業組合の推移
- 農業における生産協同組合の法制化過程
- 農事組合法人の事例
- 農事組合法人が増える理由
第5章 日本の労使関係
- 経営権と経営
- 企業別労働組合の弱点と転換方向
- 三菱重工の場合
- 中小企業家同友会の描く経営者像と労使関係
- 中小企業における労使のコミュニケーションの仕方
- 労使協議制の行方
第6章 労働者自主生産と協同組合化の道
- 企業倒産による労働者自主生産
- 労働者協同組合に転進する条件
第7章 市民事業型の協同労働の発展
- 新しい波
- ワーカーズ・コレクティブ・ネットワーク・ジャパン(WNJ)
- 日本労働者協同組合連合会
- 農山漁村の村おこしグループ
- 障害者就労作業所グループ
- 「協同労働の協同組合」法の制定を要請する市民会議
- 憲法27条のミステリーと「協同労働の協同組合」の法制化
結びにかえて
参考文献
あとがき
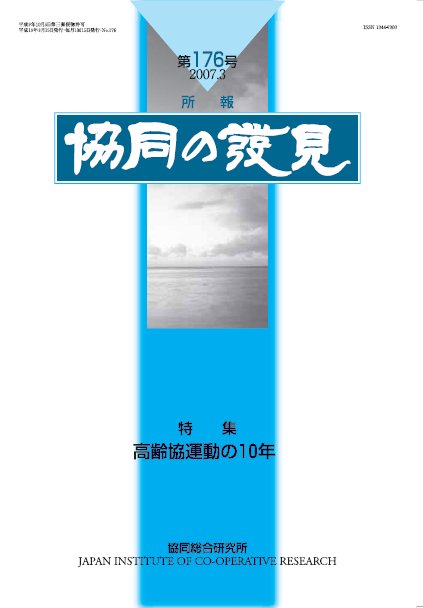 高齢者協同組合運動が始まっておよそ10年が経過しました。この10年で確実に少子高齢社会は進行する一方で、医療、福祉、年金の構造はいまだ大きく改革が進みません。新たな貧困や格差が社会的な課題となる中で、団塊世代の大量リタイアもあいまって、豊かな社会をつくりだす主体としての高齢者協同組合運動は大きな期待を集めています。
高齢者協同組合運動が始まっておよそ10年が経過しました。この10年で確実に少子高齢社会は進行する一方で、医療、福祉、年金の構造はいまだ大きく改革が進みません。新たな貧困や格差が社会的な課題となる中で、団塊世代の大量リタイアもあいまって、豊かな社会をつくりだす主体としての高齢者協同組合運動は大きな期待を集めています。 研究会では、まず協同総合研究所の岡安専務理事が「韓国の社会的企業法をめぐって」と題して報告。欧州各国における近年の社会的企業・社会的協同組合に関わる法整備を概観した後、ここ数年の韓国労働者協同組合連合会や自活後見機関との交流から「社会的企業育成法」が昨年末に成立した経緯、法の内容(
研究会では、まず協同総合研究所の岡安専務理事が「韓国の社会的企業法をめぐって」と題して報告。欧州各国における近年の社会的企業・社会的協同組合に関わる法整備を概観した後、ここ数年の韓国労働者協同組合連合会や自活後見機関との交流から「社会的企業育成法」が昨年末に成立した経緯、法の内容( 続いて、東京市政調査会主任研究員の五石敬路さんより、「社会的企業法の背景」として報告がありました。五石さんはまず、韓国の社会的企業育成法が低所得者層・貧困層の運動から生まれてきた点が、日本との比較で最も大きく異なる点とした上で、韓国における貧困層の運動の歴史を説明しました。
続いて、東京市政調査会主任研究員の五石敬路さんより、「社会的企業法の背景」として報告がありました。五石さんはまず、韓国の社会的企業育成法が低所得者層・貧困層の運動から生まれてきた点が、日本との比較で最も大きく異なる点とした上で、韓国における貧困層の運動の歴史を説明しました。 自活支援事業をめぐる問題としては、生産性の向上や自立者の拡大など事業の成果が上がらないとの批判や、運動側としてもコミュニティ運動の文脈で発展させていきたいという思いがありながら、自活後見機関から脱して自立すると却って生活が苦しくなる「貧困の罠」の問題、また制度的によって参加者が決められるため、共同体の理念の維持が難しいことなど、いくつかの問題点を挙げられました。
自活支援事業をめぐる問題としては、生産性の向上や自立者の拡大など事業の成果が上がらないとの批判や、運動側としてもコミュニティ運動の文脈で発展させていきたいという思いがありながら、自活後見機関から脱して自立すると却って生活が苦しくなる「貧困の罠」の問題、また制度的によって参加者が決められるため、共同体の理念の維持が難しいことなど、いくつかの問題点を挙げられました。