|
||
| 協同のひろば | ||
| 市民の手による持続可能な住宅地づくりⅠ ―ドイツ・フライブルク・ヴォーバン地区(Vauban)― |
||
| 堀越真紀子(東京都/協同総研) | ||
|
大聖堂
 ○環境首都フライブルク ○環境首都フライブルクドイツ南西、中世の町並みを残したフライブルクに、社会的コミュニティの形成と環境共生住宅の実現を目的とした、市民の手によるニュータウンがある。この「ヴォーバン地区」は街の中心からバスで10分ほどのところ、フライブルク市の南東に位置している。92年までは旧フランス軍基地であったが、ドイツ連邦に返還後、市はこの地域を買い受け、ニュータウン計画を立てることとなった。そこでこの地区を環境に配慮したエコタウンにしようと、市民はNPO「フォーラム・ヴォーバン」を設立し、建設当初から市と協力してニュータウンの開発を行なっている。フライブルクでは市民活動が盛んに行なわれており、市もそれに協力して積極的に環境政策を進めているのである。 フライブルクは環境首都、ソーラー首都などと呼ばれ、日本でも文献やマスコミなどで広く紹介されている。そう呼ばれるきっかけは、1970年代のヴィールという近郊の町での原子力発電所建設計画に対する長期にわたる反対運動からであった。地域住民の反対運動で発電所の建設計画が阻止された後、その運動は原子力に代わる代替エネルギーを導入する活動、環境保護運動へと代わっていく。そして市も環境政策に積極的に取り組み始めるようになるのである。現在、ドイツ最大の環境保護団体BUND(ドイツ環境保護連盟)や国際的組織のICLEI(国際環境自治体協議会)のヨーロッパ事務局など環境団体の本部や支部、太陽エネルギー研究を行なうフラウエンホファー・ソーラーエネルギーシステム研究所をはじめとする研究機関、市民団体などが90以上あり、市の環境政策を引っ張っている。 人口およそ20万人のフライブルクはフランス、スイスの国境近くに位置し、黒い森に囲まれた自然豊かな街である。また、500年以上の歴史のあるフライブルク大学をはじめ、音楽大学などいくつかの大学があり、日本人を含めて多くの留学生も学ぶ大学街でもある。歴史的街並みの旧市街には、中世に防火、清掃のためにつくられた幅30センチほどの小川がはりめぐらされ、近くのドライザーム川から黒い森の水が流れている。天気の良い日に、車の乗り入れが規制されたこの地区の石畳を小川沿いにぶらぶらと散歩すると、静寂のなかでヨーロッパの歴史を感じることができるし、水の流れがとてもここちよい。 フライブルクで一番の歴史的シンボルは大聖堂(ミュンスター)であろう。旧市街の中心広場にそびえたつ大聖堂は1200年ごろから300年以上かけてつくられ、今でも修復作業は続く。過去幾度もの戦争を見てきたであろう大聖堂に残る鉄砲の傷跡は生々しい。そうした中世の歴史が色濃く残るフライブルクも、大聖堂は奇跡的に全壊を免れたものの、第二次世界大戦の空爆で瓦礫の山と化してしまった。現在残る歴史的な建造物は大戦前と同じようにそのまま復元したものだそうで、かつての邸宅や修道院は博物館としてよみがえり、中央広場沿いにあるかつての商館、歴史的商品取引所は集会や会議、音楽界などの催し物に使われている。いつも多くの人でにぎわう広場では、新鮮な野菜や果物、花が並ぶ朝市が立ち、12月にはクリスマス市が出たり、時には職人や芸術家の展示即売が行われたりすることもある。 もともとフライブルクは観光地としても有名で多くの観光客が訪れる都市であるが、近年では環境に対する取り組みを視察する団体も多く訪れ、訪問者は年々増加しているようである。そういう私もドイツでエコロジカルな生活をし、調査してみたいとこの街に滞在していた1人であるが、当時よく日本人の視察団を見かけることがあった。フライブルクのさまざまな環境への取り組みのなかでも今回は、ニュータウン・ヴォーバンにおける市民による住宅地づくりを紹介したい。 ○市民参加の持続可能な地区づくり (ヴォーバン計画図) 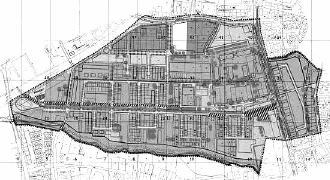 ヴォーバンニュータウンの管理、運営を行なっているNPO「フォーラム・ヴォーバン」は、いろいろな社会層や年齢の人たちがともに住み、働くことのできるエコロジカルな住宅地の実現を目指している。その設立は1994年、ヴァーバン地区の都市計画への市民参加を目的としてはじまった。会員数は約300である。運営はオフィススタッフとボランティア、他の団体との協力により行なわれている。フォーラムは市民側の代表としてこの地区の設計当初から計画に関り、持続可能な地区づくりに向けてワークショップを開くなど様々な活動を行なってきた。そして1995年、フライブルク市は2006年までに5000人の住宅を建設することと600の雇用を創出することを決定した。フォーラムは、ニュータウン計画が市議会で決議される前に行われる「市の活動グループ会議」のメンバーとして、ヴォーバン地区の開発に関する討議に参加している。そして、エネルギー、交通、建築の分野において、市とフォーラム・ヴォーバン、FEW(フライブルクエネルギー・水供給公社)、GENOVA(住宅協同組合ヴォーバン)、ICLEI(国際環境自治体協議会)、その他の機関、建築業者とが協力し、持続可能なモデル地区づくりを目指したヴォーバン地区のニュータウン建設が推進されることとなった。 ヴォーバンニュータウンの管理、運営を行なっているNPO「フォーラム・ヴォーバン」は、いろいろな社会層や年齢の人たちがともに住み、働くことのできるエコロジカルな住宅地の実現を目指している。その設立は1994年、ヴァーバン地区の都市計画への市民参加を目的としてはじまった。会員数は約300である。運営はオフィススタッフとボランティア、他の団体との協力により行なわれている。フォーラムは市民側の代表としてこの地区の設計当初から計画に関り、持続可能な地区づくりに向けてワークショップを開くなど様々な活動を行なってきた。そして1995年、フライブルク市は2006年までに5000人の住宅を建設することと600の雇用を創出することを決定した。フォーラムは、ニュータウン計画が市議会で決議される前に行われる「市の活動グループ会議」のメンバーとして、ヴォーバン地区の開発に関する討議に参加している。そして、エネルギー、交通、建築の分野において、市とフォーラム・ヴォーバン、FEW(フライブルクエネルギー・水供給公社)、GENOVA(住宅協同組合ヴォーバン)、ICLEI(国際環境自治体協議会)、その他の機関、建築業者とが協力し、持続可能なモデル地区づくりを目指したヴォーバン地区のニュータウン建設が推進されることとなった。 こうしたヴォーバンの取り組みは国際的にも注目されている。イスタンブールで行われた国連の世界住宅会議HABITATⅡ(1996年)においては、都市計画における市民と行政が協力した模範例として「ドイツで最高の事例」と紹介された。 また、「ヴォーバン持続可能なモデル地区づくり」計画は、1997年から99年まで、EUの環境プロジェクト「LIFE」から支援を受けることができた。具体的には、省エネハウス、車のない住宅、エコロジーハウスの建設や、ソーラー機器の設置に対して助成金などの財政的支援が行なわれ、建設業者にはエコロジカルな建築に関する情報や環境にやさしい交通・モビリティについての助言が数多く提供された。このプロジェクトは、ヴォーバンでエコハウスを建てることに対して関心が高まるきっかけともなっている。 〇共同建築とコミュニティづくり フォーラム・ヴォーバンは持続可能なニュータウンづくりを目指し、次の目標を掲げている。 ・ ニュータウンの計画、建築プロセスにおける広範囲に及ぶ市民参加 ・ 民間の建設共同体の設立支援ならびに建築業者への助言に対する支援 ・ 社会的でエコロジカルなモデル地区の実現 フォーラムが目的とする「市民参加」は、住民会議などの各種催し、広報活動、情報誌「Vauban actuel」の発行を行ったり、相談所を設立して建設組合や建設者に対し情報を提供したり、エネルギー、交通、女性と社会、建築などをテーマとする実践的な研究サークルをつくるなど多様な分野において展開されている。 このような活動から、例えば「エコハウスの建築」「自家用車のない住居」などというコンセプトを持った建築グループや住宅組合がつくられ、共同で住宅の建設を行っている。こうした手法がヴォーバン住宅建設の特徴の1つでもある。エコハウスを建てたい、住みたいと思っても価格や技術面で問題が生じるが、複数の人々がグループをつくり土地を購入して1つの建物の建築を目的に学習会を開き、設計したり、ときには自ら作業に参加したりすることで価格も抑えられ、情報も共有できる。集合住宅ならば太陽光発電装置などの設備を共有できるのでエネルギー消費も少なくてすむ。また、共同で計画段階から話し合って作業を行なうことで、これから同じ住宅に住む隣人と入居前からコミュニケーションがとれ、おたがいにより深く知り合うことができるという利点がある。 ヴォーバンではこうした建築グループのほかに、GENOVAという住宅組合による住宅の建設も行なわれている。GENOVAは1997年、社会的コミュニティとエコロジカルな住宅をつくる目的でフォーラムヴォーバンから設立された。設立当初の組合員は90人で、自己責任と自己労働、共同建築と居住、共有財産の構築といった伝統的な協同組合の目標をふまえている。住民は積極的に設計段階から住宅建設に参加し、自分の住居はもちろん、住宅全体の位置や形、色などの外観にもこだわった。若者も高齢者も、異なる年齢層が価格の安いエコロジカルな住宅に住むというコンセプトの下に、様々な生活形態で社会的、経済的に不当に扱われている人たちもこのプロジェクトに参加している。 1998年から第1次建設区画で建築が始まり、44㎡から157㎡の36の住居と、客室、洗濯室からなる50㎡の共有ハウスを持つ賃貸住宅が完成した。高齢者が、そして現在の住人が高齢者になっても自立して生活できるようにということで、2階までの住居は全てバリアフリーになっている。そして第2次建設区画では、「車のない暮らし」をコンセプトに40世帯の住宅を建設している。 150世帯が参加する建築グループが第1次建設区画では15もつくられ、第2次建設区画ではさらに10の建築グループが結成された。そして住宅組合GENOVAは2005年までに約70の住宅を建築する予定である。このように共同の住宅建設をとおして議論を重ね、家族のことやおたがいを理解していきながら、ヴォーバンでは子どもや高齢者を持つ家族、シングル、母子・父子家庭、店舗経営者が出会うコミュニティがつくられているのである。 ○自然エネルギー住宅に住む―パッシブハウスとプラスエネルギーハウス (太陽発電装置を備えたプラスエネルギーハウス)  ヴォーバンの魅力は多様な建物と人々、そして車の通らない子ども達のための遊び場、緑に囲まれた暮らしである、と語る「アクティブ・パッシブ」という建築グループは、フォーラム・ヴォーバンで知り合ったエコハウスに関心のある4家族によって結成された。その後2家族が加わって18人の大人と24人の子供たちが参加するグループとなり、ドルフバッハという小川沿いの第2次建設区画にパッシブハウス(省エネ住宅)を建てた。パッシブハウスとは太陽熱を受けて暖房エネルギーとして利用する、いわゆる省エネルギー住宅のことである。フライブルクの建築基準によると、1平方メートルあたりの年間の暖房エネルギー消費量は最大65キロワット時以下でなければならないと定められている。ドイツの平均的な家庭で100から200キロワット時なのでフライブルクの基準はかなり低めに設定されているが、パッシブハウスはこれよりもさらに低いエネルギー消費の15キロワット時以下である。このグループのパッシブハウスでは、南の大きな窓から太陽熱を取り入れ、熱効率をあげるために北側の壁や屋根の断熱を強化している。そして一般的に使用されているガスを使った温水暖房ではなく、太陽熱を利用した温水器を設置することで暖房エネルギーを自給自足している。(ドイツの暖房は主に温水によるセントラルヒーティングである。) ヴォーバンの魅力は多様な建物と人々、そして車の通らない子ども達のための遊び場、緑に囲まれた暮らしである、と語る「アクティブ・パッシブ」という建築グループは、フォーラム・ヴォーバンで知り合ったエコハウスに関心のある4家族によって結成された。その後2家族が加わって18人の大人と24人の子供たちが参加するグループとなり、ドルフバッハという小川沿いの第2次建設区画にパッシブハウス(省エネ住宅)を建てた。パッシブハウスとは太陽熱を受けて暖房エネルギーとして利用する、いわゆる省エネルギー住宅のことである。フライブルクの建築基準によると、1平方メートルあたりの年間の暖房エネルギー消費量は最大65キロワット時以下でなければならないと定められている。ドイツの平均的な家庭で100から200キロワット時なのでフライブルクの基準はかなり低めに設定されているが、パッシブハウスはこれよりもさらに低いエネルギー消費の15キロワット時以下である。このグループのパッシブハウスでは、南の大きな窓から太陽熱を取り入れ、熱効率をあげるために北側の壁や屋根の断熱を強化している。そして一般的に使用されているガスを使った温水暖房ではなく、太陽熱を利用した温水器を設置することで暖房エネルギーを自給自足している。(ドイツの暖房は主に温水によるセントラルヒーティングである。)第1次建設区画でも「LIFE」プロジェクトの支援を受けて、すでに42世帯のパッシブハウスが建設されており、ドイツで最初の4階建パッシブ集合住宅となった。第2次建設区画の40世帯以上のパッシブハウスを含め、現在、ヴォーバンはドイツで最大のパッシブハウス団地といわれている。  シュリアーベルクという山のふもとの旧フランス軍運動場は、プラスエネルギーハウスが立ち並ぶソーラー住宅地区となっている。プラスエネルギーハウスとは、太陽光発電によって住む人が消費するエネルギーよりも多くのエネルギーを生み出す住宅のことで、必要な暖房エネルギーは熱の再利用と断熱、換気を高めることで最小限に抑える。あまったエネルギーは1キロワット時99ペニヒ(約60円)で電力会社に販売することができる。そしてこのハウスで必要な暖房エネルギーは従来の住宅の10分の1ですむという。ヴォーバンのソーラー地区では150ものプラスエネルギーハウスが建設予定となっており、全ての屋根にソーラー発電装置が取り付けられることになっている。そのプラスエネルギー住宅を設計、建設しているのはソーラー建築家として有名なラルフ・ディシュ氏である。彼はフライブルクのさまざまなソーラーエネルギー政策に関っており、学校やサッカースタジアム、工場など現在ある建物にソーラーパネルを設置するなどさまざまな活動を行なってきた。エネルギーを消費するだけではなくて生み出す家を、ということで実験的につくられた家がヘリオトロープという太陽の動きに合わせて回転するソーラーハウスである。住宅街に建てられているこのハウスはユニークな形をしていて、見たところ住宅には見えないが、彼は家族と共にここに住んでいるそうだ。2000年に行なわれたハノーファー万博では、フライブルクの他のソーラー施設とともにこのプラスエネルギーハウスが紹介、展示され、注目されたそうである。 シュリアーベルクという山のふもとの旧フランス軍運動場は、プラスエネルギーハウスが立ち並ぶソーラー住宅地区となっている。プラスエネルギーハウスとは、太陽光発電によって住む人が消費するエネルギーよりも多くのエネルギーを生み出す住宅のことで、必要な暖房エネルギーは熱の再利用と断熱、換気を高めることで最小限に抑える。あまったエネルギーは1キロワット時99ペニヒ(約60円)で電力会社に販売することができる。そしてこのハウスで必要な暖房エネルギーは従来の住宅の10分の1ですむという。ヴォーバンのソーラー地区では150ものプラスエネルギーハウスが建設予定となっており、全ての屋根にソーラー発電装置が取り付けられることになっている。そのプラスエネルギー住宅を設計、建設しているのはソーラー建築家として有名なラルフ・ディシュ氏である。彼はフライブルクのさまざまなソーラーエネルギー政策に関っており、学校やサッカースタジアム、工場など現在ある建物にソーラーパネルを設置するなどさまざまな活動を行なってきた。エネルギーを消費するだけではなくて生み出す家を、ということで実験的につくられた家がヘリオトロープという太陽の動きに合わせて回転するソーラーハウスである。住宅街に建てられているこのハウスはユニークな形をしていて、見たところ住宅には見えないが、彼は家族と共にここに住んでいるそうだ。2000年に行なわれたハノーファー万博では、フライブルクの他のソーラー施設とともにこのプラスエネルギーハウスが紹介、展示され、注目されたそうである。その他にもヴォーバンではソーラーパネルや太陽熱温水器を設置した家が数多く建てられている。第1次建設区画だけでも合計面積にしておよそ300㎡の太陽熱温水器が設置され、暖房、給湯に使われている。また600人分の暖房、給湯をまかなう143㎡の太陽熱集熱機が設置されている学生寮では発電も行なわれている。ヴォーバンではFEW(フライブルクエネルギー・水供給公社)の協力を得て、中央熱源からの遠隔暖房、発電ではなく、近距離からの暖房、電力ラインが整備されているので、あまったエネルギーは無駄なく他の住宅へ供給される。こうして住民が協働で家を建てるところからはじまって、ヴォーバンは自然エネルギーの自給自足へと進んでいるのである。 ○おわりに 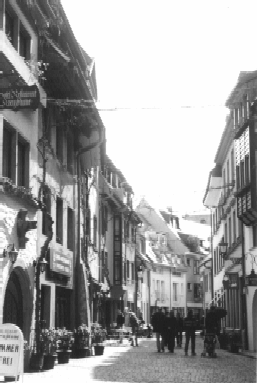 今回ヴォーバンの取り組みを紹介することで、あらためてヴォーバンの持続可能な街づくりの実践にとても大きなパワーを感じた。もしかしたらヴォーバンはフライブルクの「ソーラー発電所」となるかもしれないと思ってしまう。そのほかにもヴォーバンでは交通や緑地づくり、ごみ処理など、環境に対する取り組みが積極的に行われている。しかし、必ずしもドイツ人がみんな環境のことを考えて生活をしているわけではない。例えばごみに関していえば、お店に行っても買い物袋をくれなくいし有料だから袋を持参する、ごみを出すのはお金がかかるからなるべく出さない、という具合である。フライブルクでは環境に配慮した制度が整っているので、それが生活の中であたり前になっているだけであろう。フライブルクと比べると日本はごみの量が非常に多いと実感する。包装用のパッケージや袋など無駄にごみになるものがあまりにも多くて、捨てるときには心苦しいと思うようになってしまった。フライブルクが環境首都と呼ばれるようになったのも長年の市や市民の活動によるところが大きいのはもちろんである。そう考えると、ヴォーバンの市と住民、専門家、多くの機関が協同で行なう持続可能なまちづくりの実践が、フライブルクの「あたり前」となって、この街は自然エネルギーを自給自足するコミュニケーション豊かな街になるかもしれないと思った。 今回ヴォーバンの取り組みを紹介することで、あらためてヴォーバンの持続可能な街づくりの実践にとても大きなパワーを感じた。もしかしたらヴォーバンはフライブルクの「ソーラー発電所」となるかもしれないと思ってしまう。そのほかにもヴォーバンでは交通や緑地づくり、ごみ処理など、環境に対する取り組みが積極的に行われている。しかし、必ずしもドイツ人がみんな環境のことを考えて生活をしているわけではない。例えばごみに関していえば、お店に行っても買い物袋をくれなくいし有料だから袋を持参する、ごみを出すのはお金がかかるからなるべく出さない、という具合である。フライブルクでは環境に配慮した制度が整っているので、それが生活の中であたり前になっているだけであろう。フライブルクと比べると日本はごみの量が非常に多いと実感する。包装用のパッケージや袋など無駄にごみになるものがあまりにも多くて、捨てるときには心苦しいと思うようになってしまった。フライブルクが環境首都と呼ばれるようになったのも長年の市や市民の活動によるところが大きいのはもちろんである。そう考えると、ヴォーバンの市と住民、専門家、多くの機関が協同で行なう持続可能なまちづくりの実践が、フライブルクの「あたり前」となって、この街は自然エネルギーを自給自足するコミュニケーション豊かな街になるかもしれないと思った。最後に、ヴォーバンの持続可能な街づくりには今回紹介したもののほかにも「車のない暮らし」や「緑地づくり」などといった重要なテーマがある。そうした取り組みはまた別の機会に紹介したい。 |